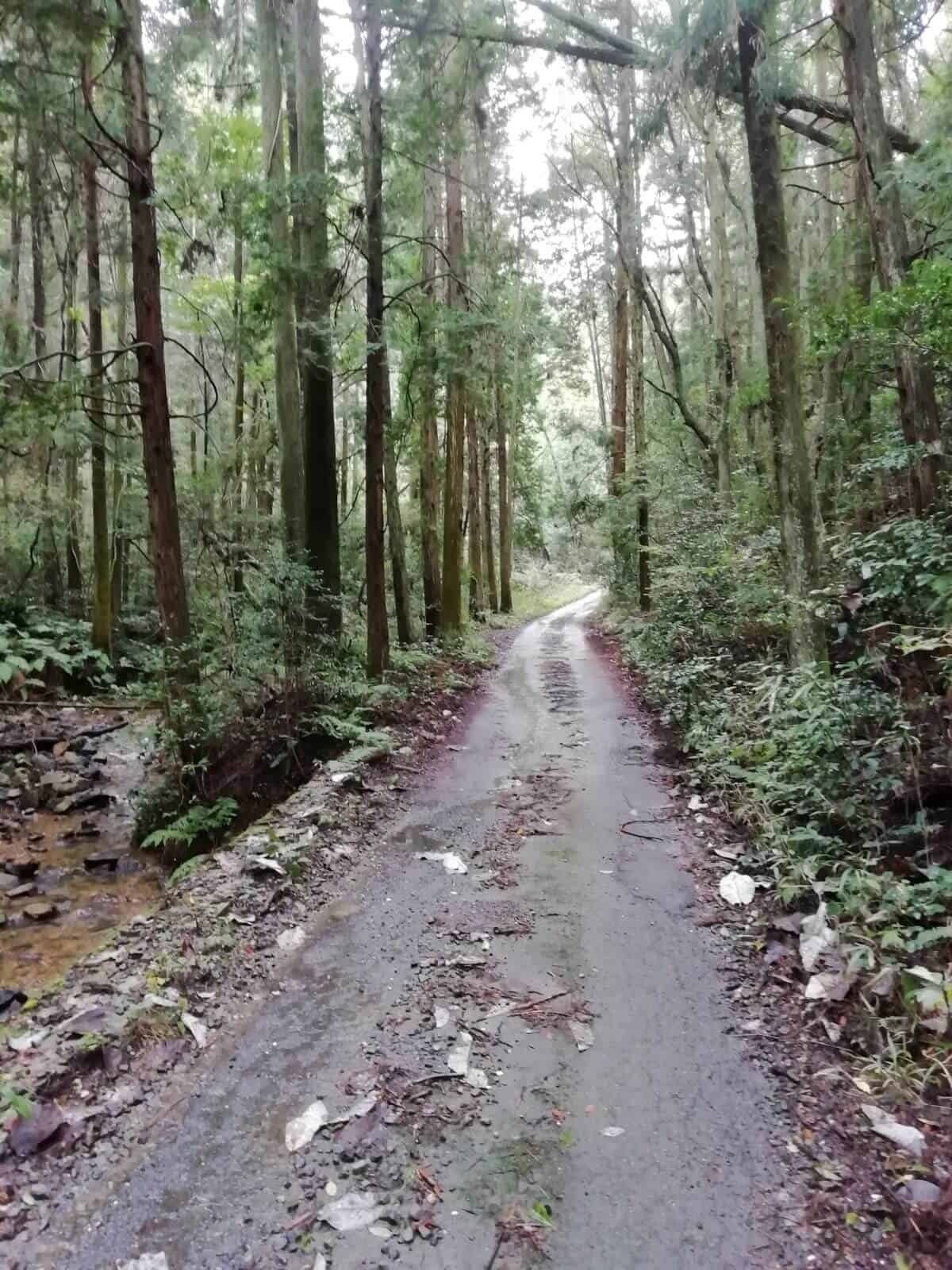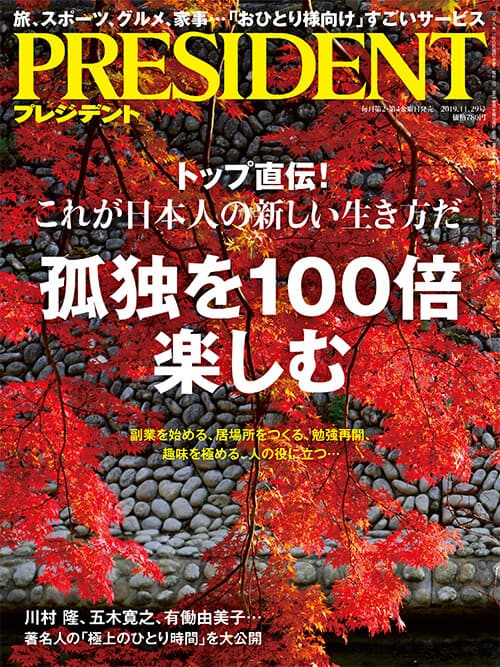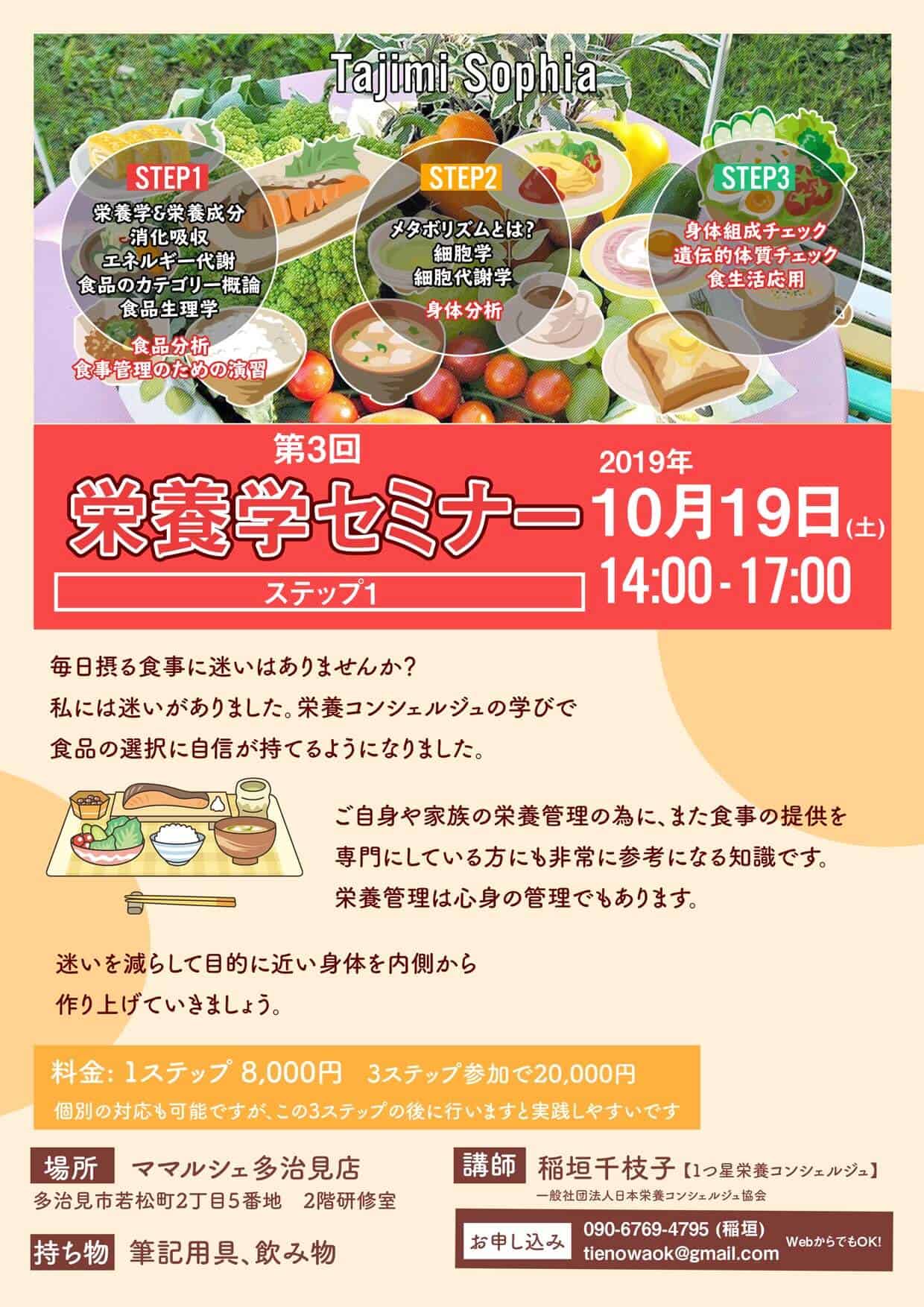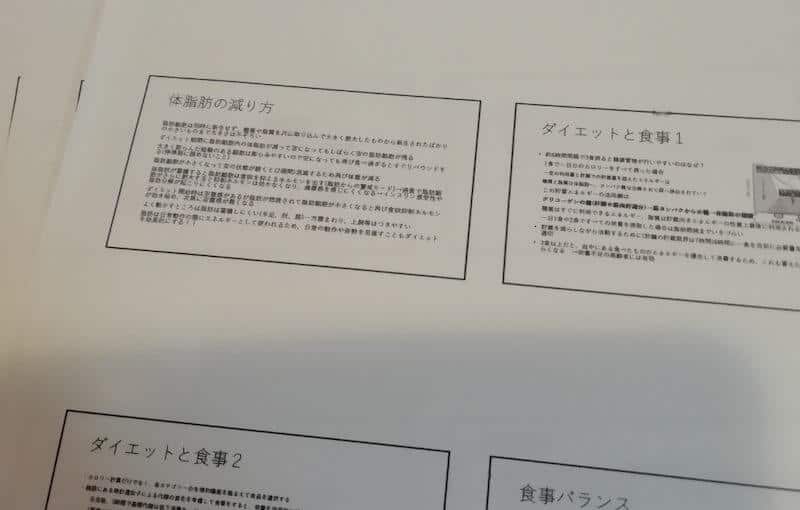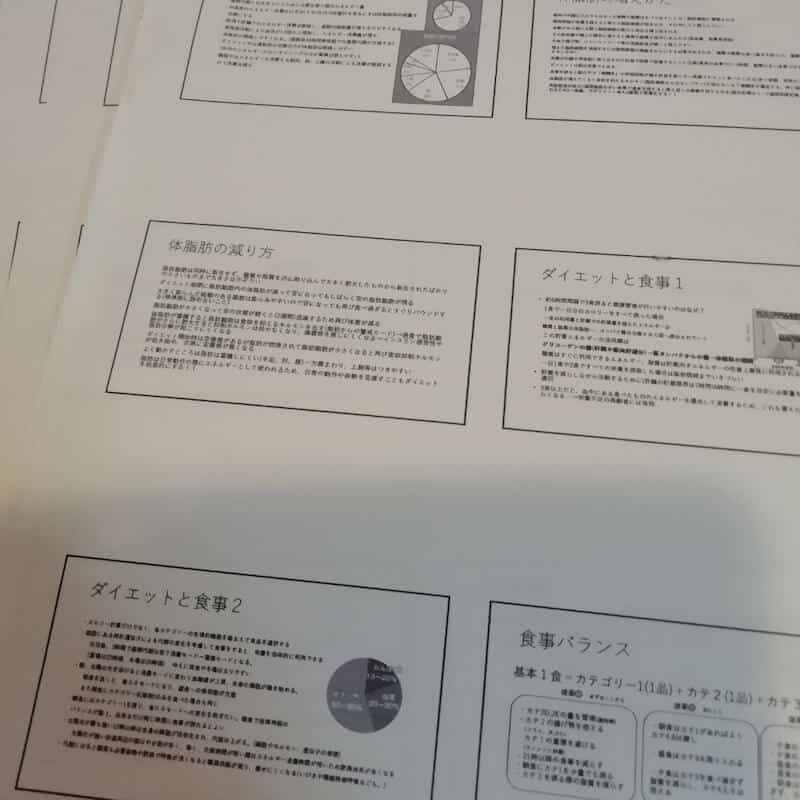アレクサンダーテクニーク京都の先生の
ボディメンタルコーチ養成講座4回目の半日セミナー。
今日は腕のボディマッピングしました
肘の骨とは?
腕の始まりの場所は?
そして腕関わる筋膜の何と広いこと!
なので来週はこんな感じで空飛ぶ翼に乗ってみましょう
ちょっとした手の使い方の工夫で
重いものを楽に運べたり
手に重心をかけて体を支えやすくなります
それから
それから
バランスのポーズとる時秘策を伝授していただきましたので
これもやっていきます
秘策
ですよ~
その名も
おっとっと体操
どうです?この名前。
秘策にしてはなんだかかわいい名前ですが
これは侮ってはいけません!
意外と単純なことに大きな解があるってものです~~

様々な分野で活躍される皆さんから様々な発言や感想が飛び交いました
一時
それは対話の中で非常に白熱化し
その場の緊張感をピークにしましたが
そのことも先生は
それすらも先生は
言葉ではなく
ボディーワークで解決の糸口を開かれました
想定外に起こる事態に対して私たちはどのような反応をするか
その場にいた私も心拍数が上がる思いでしたが
言葉ではなく
体の使い方から落ち着きを取り戻せばいい
そんな方法を目の当たりにできました
そんなエピソードもセミナーの内容と同じくとても貴重な学びの場となりました。。。。