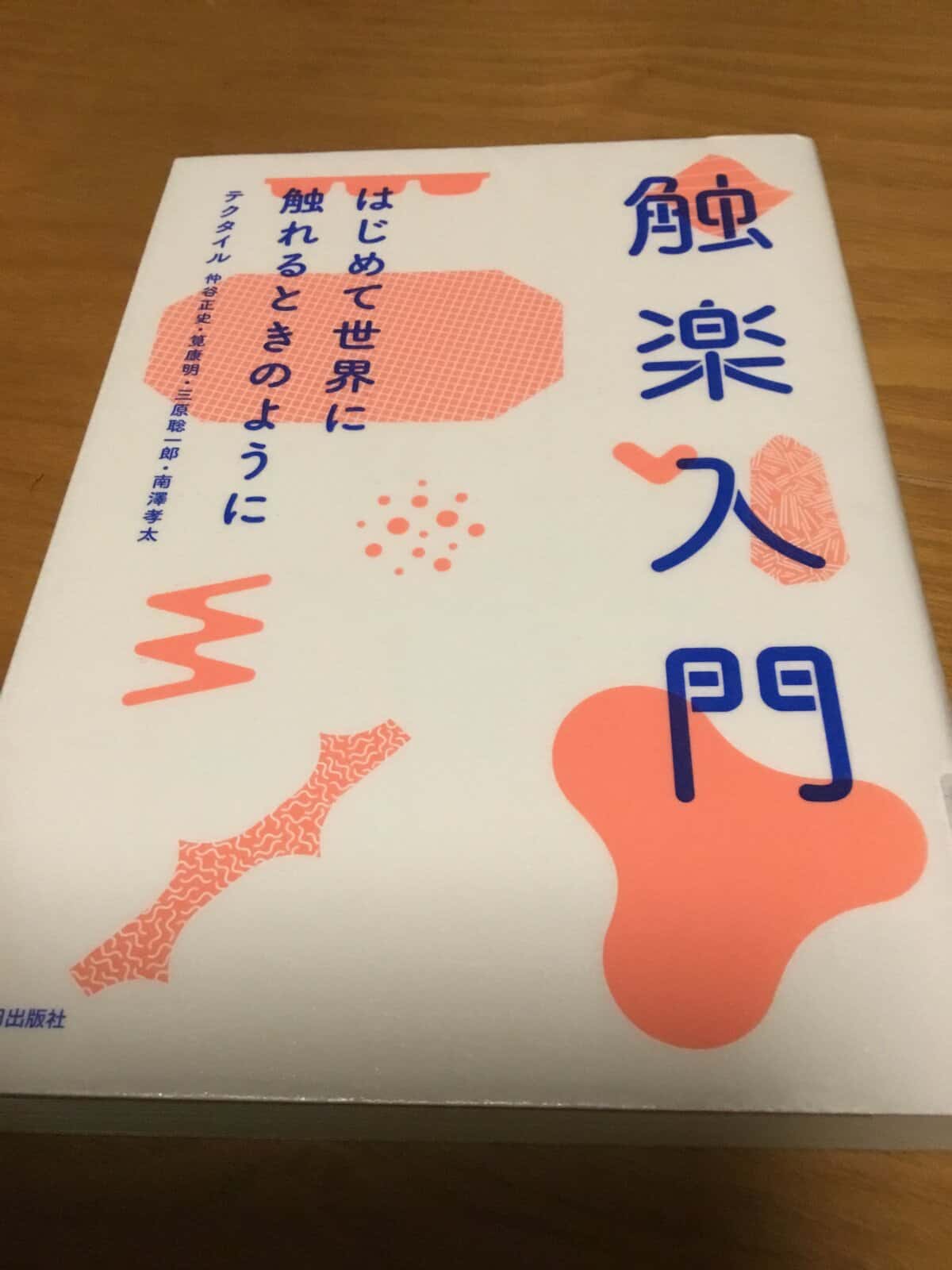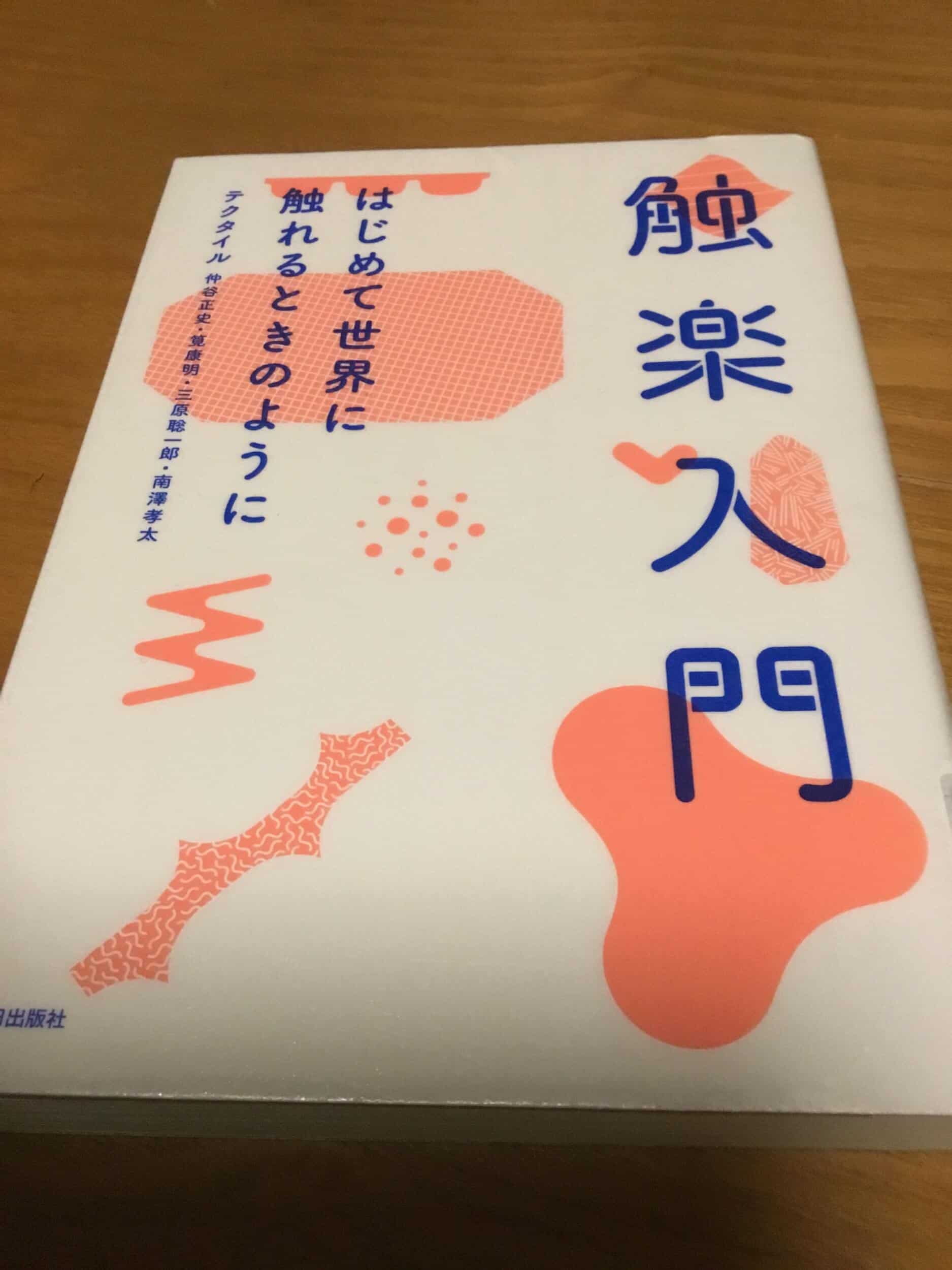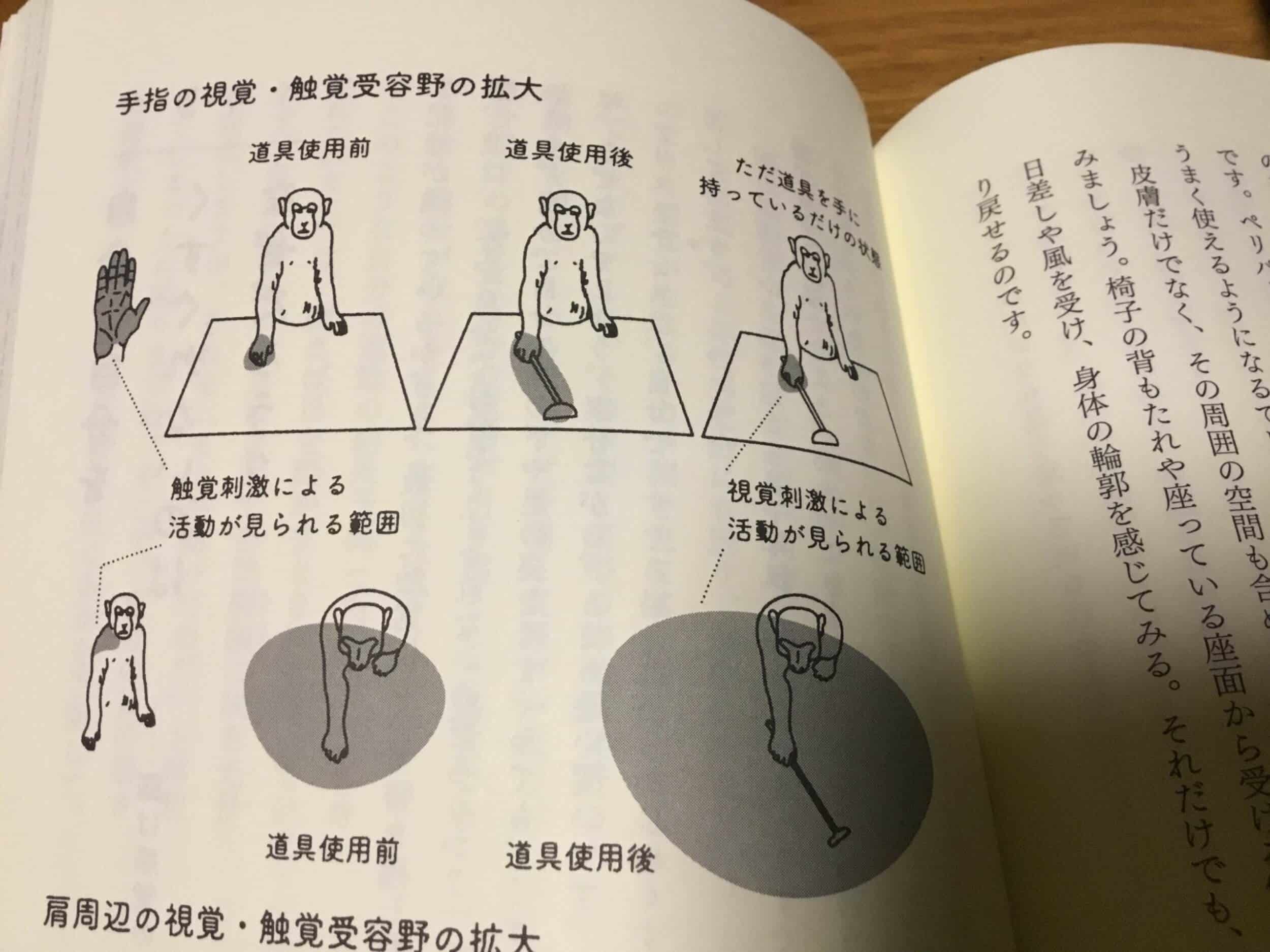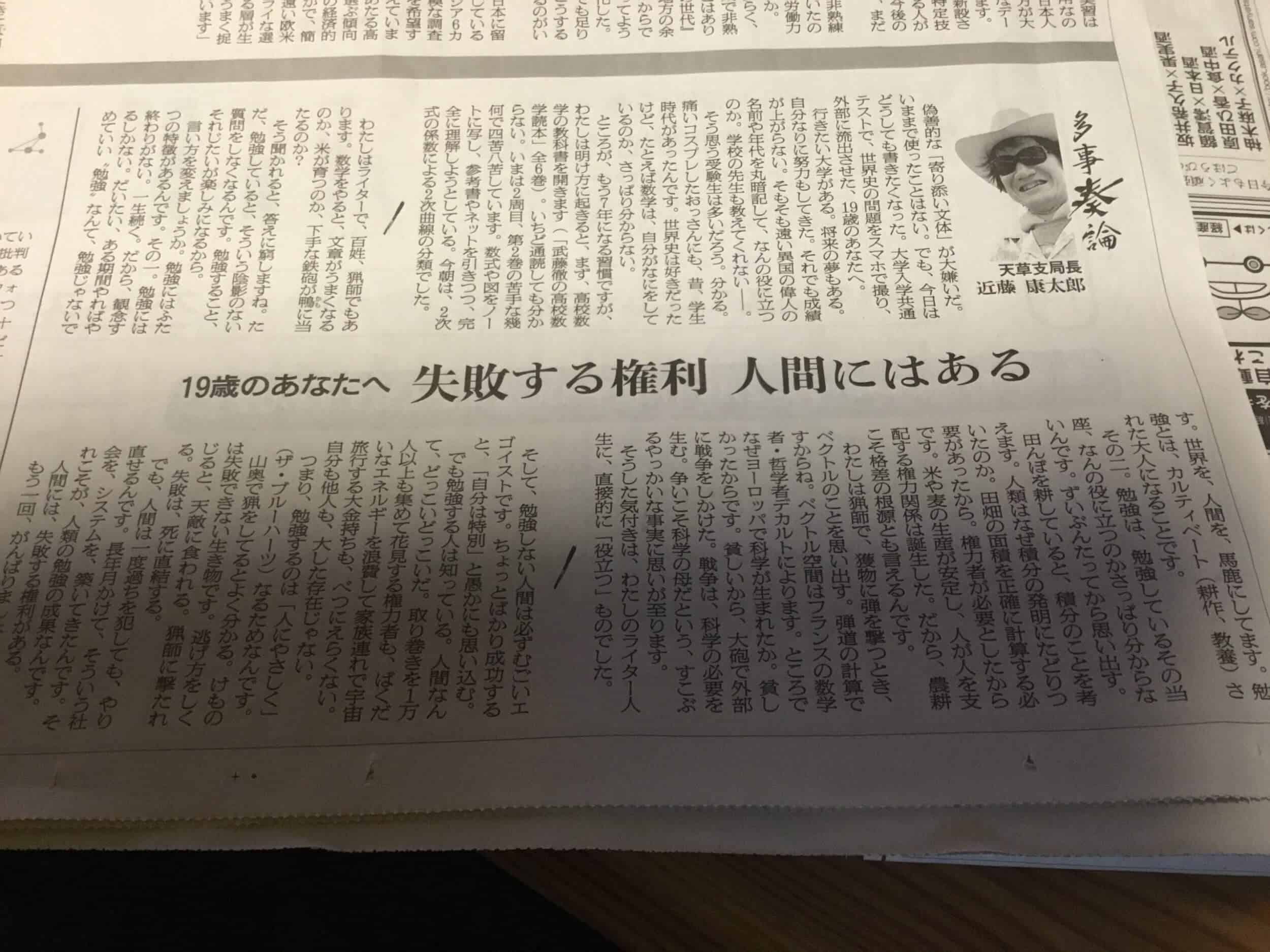自分がぎっくり腰を経験したので
❝痛み❞
のことを考えています
痛み、で気付いたことをお伝えしますね
先日この本を読みました
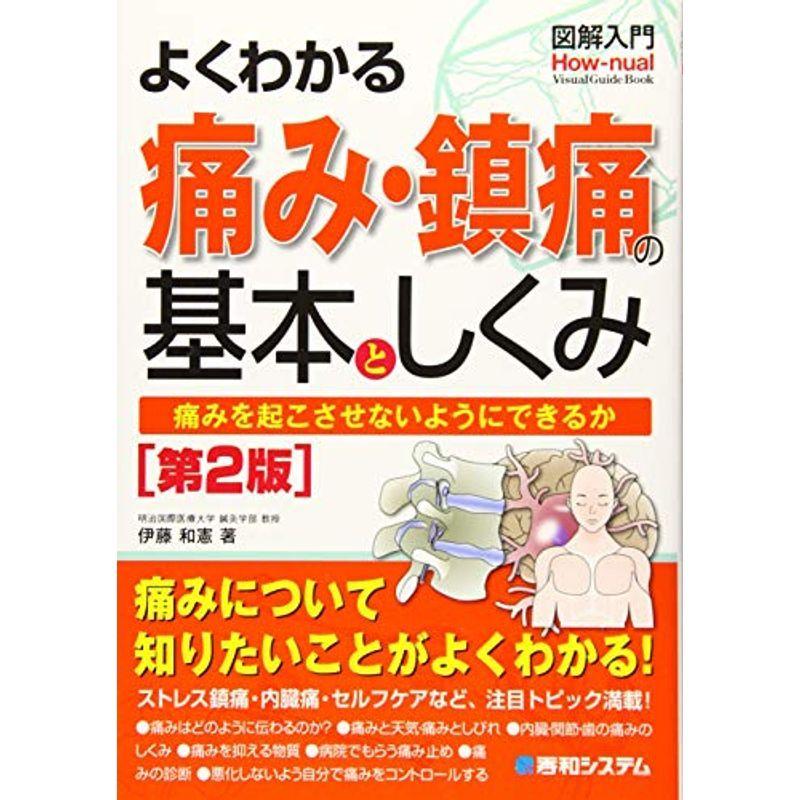
痛みは、交感神経優位(神経が興奮状態)の時に感じやすい。
なので
ストレスがある時は痛みに敏感になります
例えば
気圧が低くなると頭痛や慢性痛がひどくなる
イライラしている時に胃が痛くなる、肩がこる
睡眠不足の時に頭が痛くなるなど、、、
もちろん
痛みというのは体が送る脳へのサインなので、必要な感覚ではあります
でも
ひどい痛みは生活に支障をきたします
だから
身体は内因性の鎮痛物質を持っているのです
それが働くのはどういう時か
この本には
食事、内臓を整える、運動、前頭前野を活性化する
等があげられていました
運動によって内因性のオピオイド(鎮痛物質)が放出されることが分かっているのだそうです
前頭前野の活性化は、瞑想などの内観で可能です。
身体の観察時も同じ効果があるので
この2点はヨガでも行えます!
そして
その観察法なのですが
痛みのある局所を観察するのではなく、
『体全体を観察する』のがさらに有効かと思います
先日、スキーに訪れた勝山で温泉に行き、そこのサウナに入りました

数分間サウナで汗をかいた後で水風呂に浸かりました
冬のこの時期、水風呂に浸かるというのは結構な勇気がいります( ;∀;)
そこで気づいたのですが
足に水をかけると
きゃー冷たい!
足首まで水に浸かってもすぐに出たくなります

でも我慢して膝まで足までとだんだん浸かっていきます
お腹まで浸かってもまだ苦行状態!!!!

でも
そのまま一思いに肩まで浸かると
ん?
あれ?
そんなにつらくないのです
そこで冷水と体内の水分を同調させるようなイメージで呼吸してみると
おおお
何だか体感水温が上がったような感じがして
そのまま2、3分はいられるのです
決して苦行状態でなく、です

つまり
身体の一部分が冷たいと苦痛に感じるのですが
肩まで浸って体の大部分が水の中に入る時、苦痛は遠のきます
顔面は浸けられないので手ですくって濡らしてみましたッ
そして
その冷たさを全体で感じてみたり
また
ヨガの時にするように呼吸での背中の動きを感じてみたりしました
すると 何だか心地よささえ感じます
この観察で
冷たい!と思うと体全体が冷たいという言葉に反応して交感神経優位になると思いますが
(言葉にすると)冷たい!という皮膚表面からの刺激を、冷たい!以外の言葉、あるいは言葉にならないような皮膚感覚を味わうようにする
すると
何だか体が順応しやすくなります
❝痛い❞も全体で味わう、観察するということが可能かと思うのです
そして
痛みの時に避けた方が食品があると教えてくださった方がみえました
彼女が行っている接骨院の先生に指導されたそうです
それは・・・
*菓子類、菓子パン、清涼飲料水、果物
*カフェインを含むもの
*アルコール類
*痛み止め等の薬を最小限にする
*添加物の多い食品
等です
水分とたんぱく質は適切に摂取すべし!ということでしたよ~
以上痛みに関しての考察でした!