今日は
廿原ウォーキングの日。でした。
昨日夕方
畑で大根を抜いて来たのです。
参加された方にプレゼントしようと思って、、、
で
その後
天気を確認したらやっぱり小雨予報。
昨日は日中、何度か予報を確認してみましたが、どのサイトもあまりよさそうではなかったので
思い切って延期を決めました。
で
今日。
午前中、予定時間には雨、降りませんでしたっ💦
「ああ、行けたなあああああ」
と何度か思ってしまった一日でした。
そうそう
集合時間に小泉公民館に来てくださった方もみえました。
その方は今朝、ラインをいただいていて
「これから急遽参加してもイイですか?」
とのことだったんですが
私がオンラインレッスン中でメッセージを見逃してしまい延期を伝えそびれてしまったのです
私がラインに気が付き、急いで電話した時
彼女は小泉公民館で待っていてくれていたのです!
私もすぐ公民館に向かい事情を説明しました。
「今日は朝の雨で畑の仕事(玉ねぎの苗植え)が出来なくなったので、急に参加をきめたんです」
とのこと
事前に参加がわかっていた方だけに延期の連絡をしていたのですが
直前の参加もOKです、と言っていたので申し訳ないことをしてしまいましたッ
しかも、可児市から!
うう
有難い
そして
ごめんなさ~い(´;ω;`)
どうか
リベンジできますように~
曇りの午前中
集合場所近くの池田とその先まで歩いて行ってきました

大イチョウが半分葉を落として
見事な黄色の絨毯が出来ていました
帰り道
参加予定だったHさんの家の前を通過したら
「今日は奥さんと参加しようと思っていたけど、行けたね~」
「昨日が天気予報、いまいちで、、、」
「ま、そんなもんでしょ~」
「来月ふたりで参加するよ」
との会話。
Hさんの菊、見事でした


玄関先も

バラは奥様が

いつもキチンとされています
今日は秘密部屋を見せてくださいました

離れにある専用ジム!!
なんでも手作り
すごいなあ~
皆さま
来月お待ちしていま~す

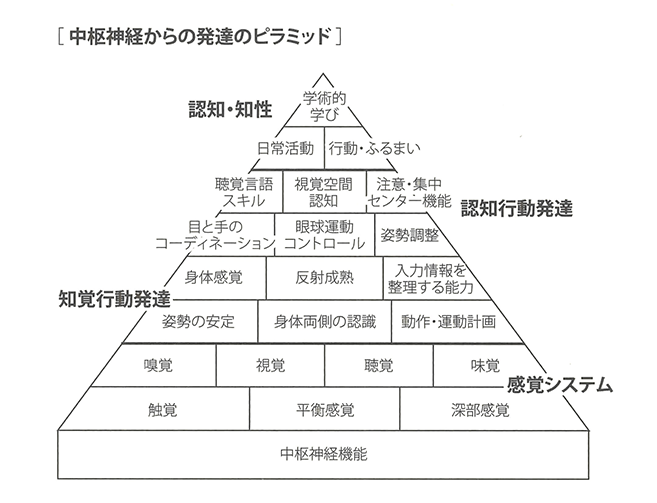
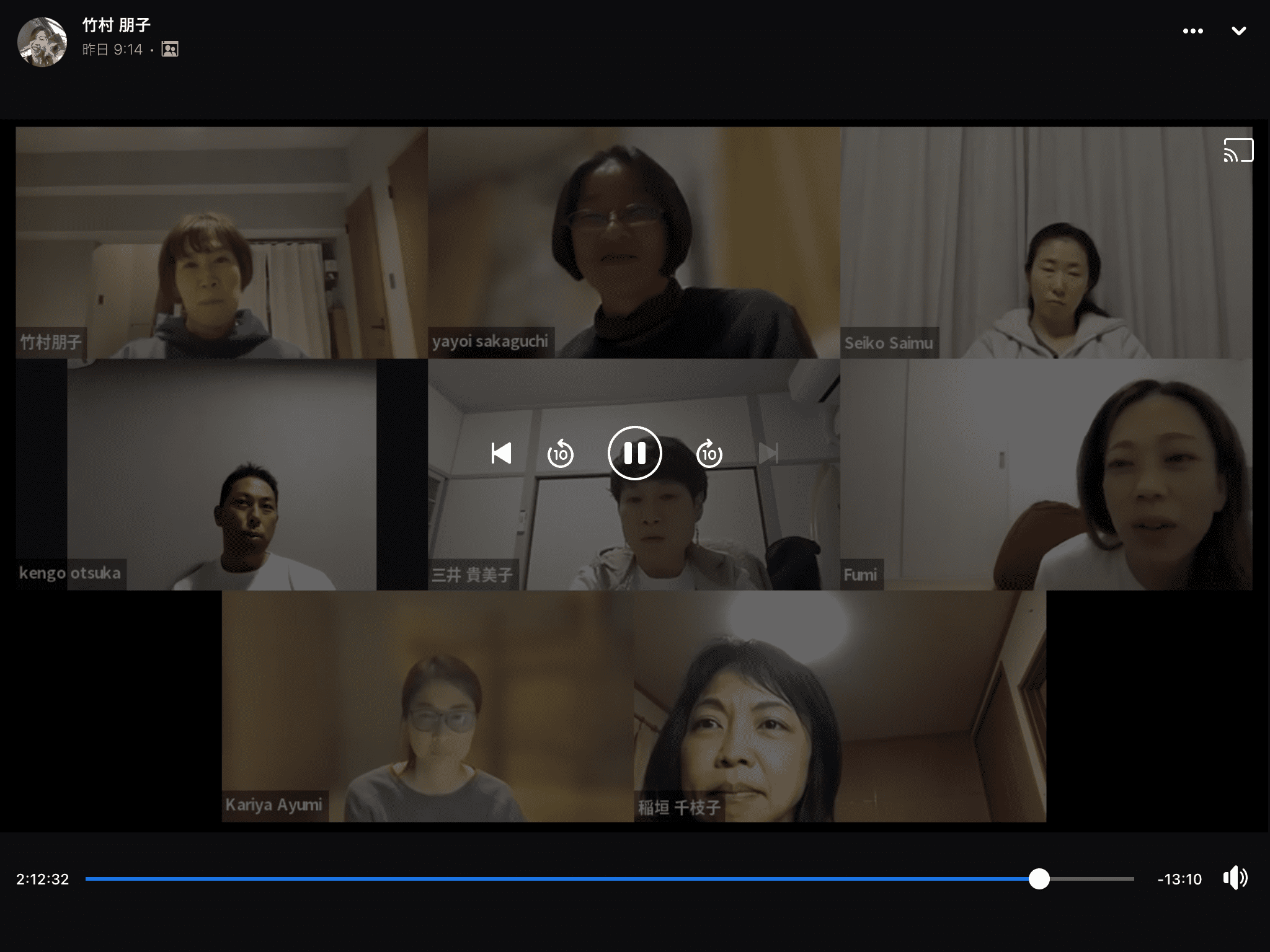




























 記念のショット
記念のショット







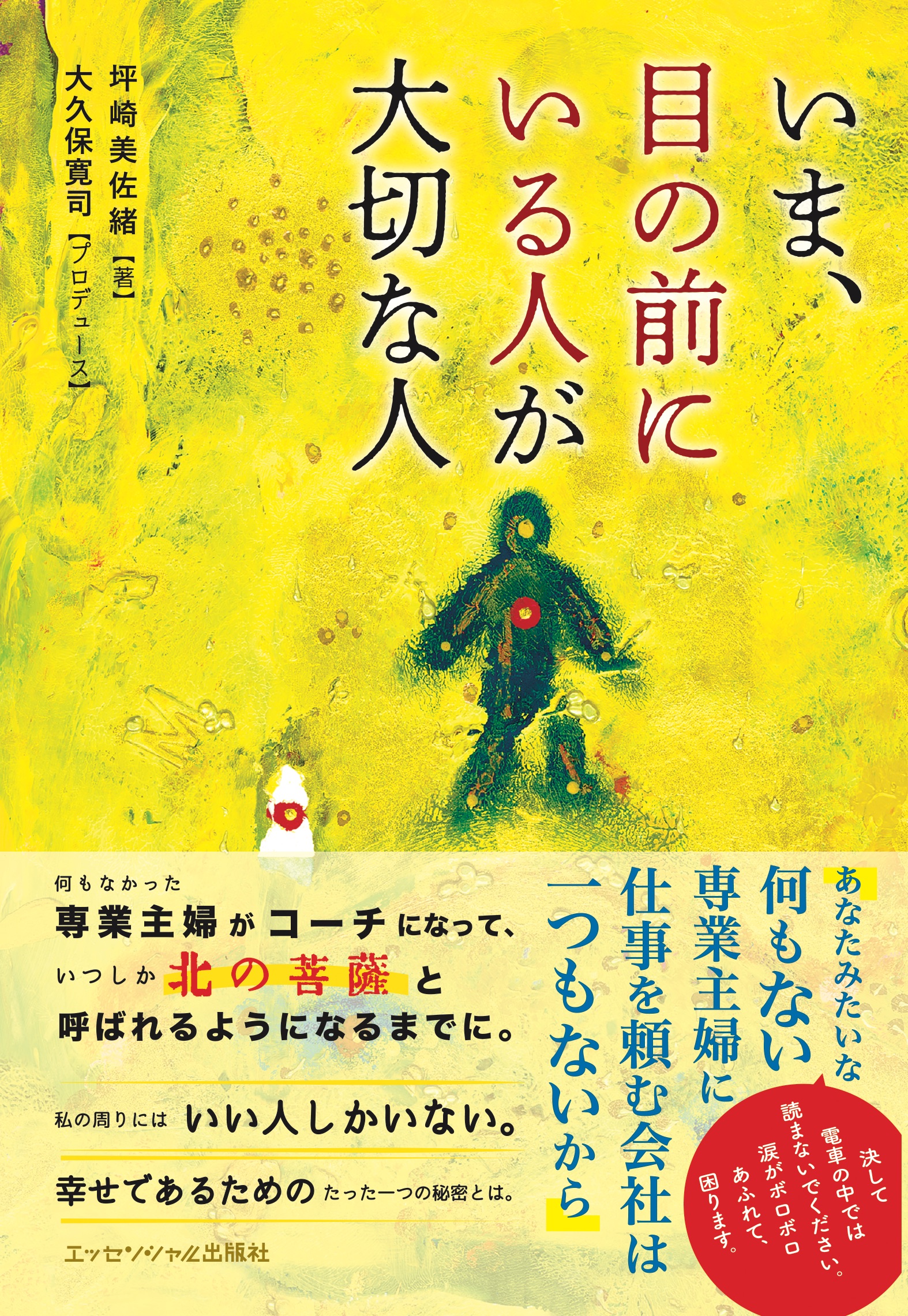















![自然の中を歩く女性の写真・画像素材[2019437]-Snapmart ...](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqGy8KbCPV2TSezKqzfz8qArGdEcSj19PBX1cLRUpo9pfRcBEnbrQxc2zAf3x1X7e1FYSFWdAOSrnJ_OGIaTHsKHxWwTIsL5v4rse-qyqZgXmQ5T6Jt1w-U9E0YRa2kZkuda3qF66mzI3WwlMxkFitIKKMEFK9rj0Y7LLyCqdJczYeXGj0Z3M2WZIW-mJveG3_f1YGFhH6RqTC_q1eFRk5JI0vr_6r-P8iXrCWNWBivuitYZj1BPbNsRIYnowzzWrgIdTggAYWEs8z1czSMQXo3RcFpGE4a_jpYX95j8I24LZOJhPetcCUIqwojjGYXb6wAw==/mp_20190413-103528998_waryq.jpg)














